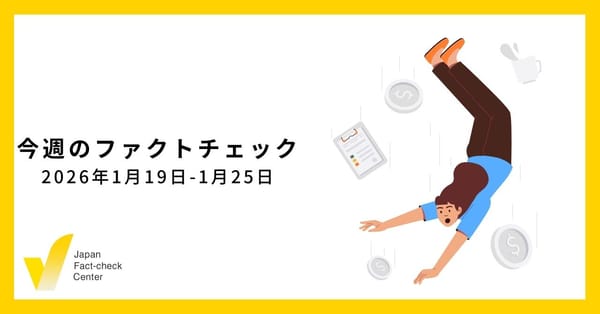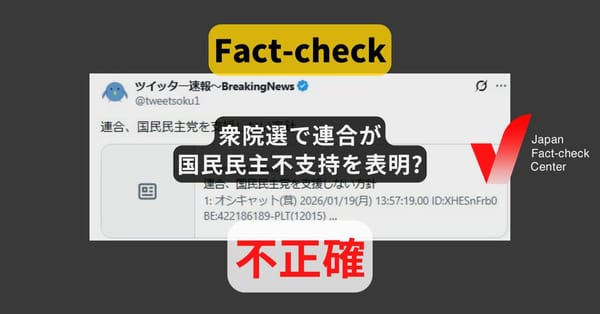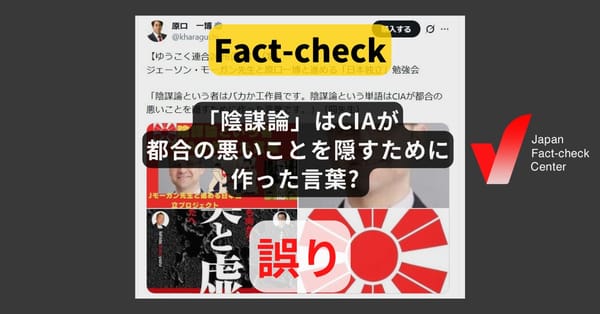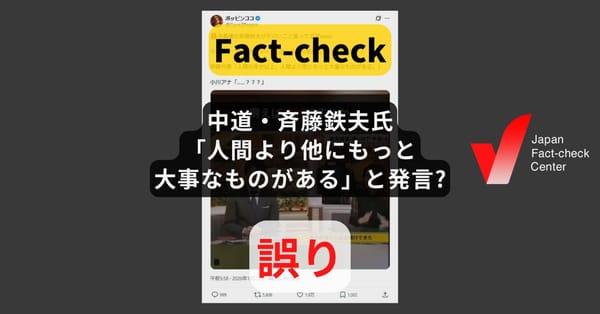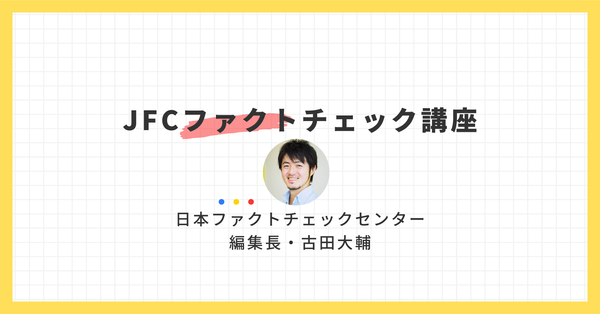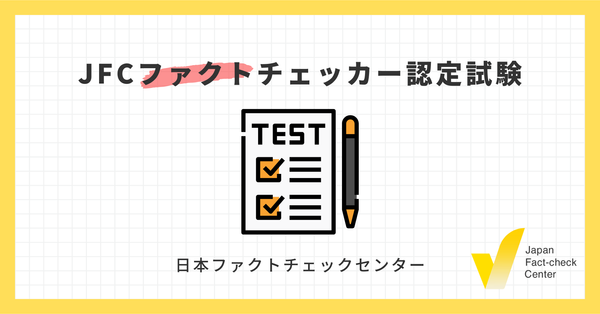熱湯で殺菌されるから輸入紅茶は細菌検査されない?【ファクトチェック】

「紅茶は熱湯で淹れる際に殺菌されるから、水出しという飲み方は想定されておらず、日本に輸入されるときに細菌の検査はない」という言説が拡散しましたが、不正確です。日本に輸入されるときに細菌検査がないのは事実ですが、厚生労働省は「現時点で紅茶の病原微生物リスクが確認されていないから」と説明しています。
検証対象
「紅茶は日本に輸入されるときに農薬の検査はされるが細菌の検査はしない。熱湯で淹れて飲むことが前提なので熱湯により殺菌されるから」「水出しという飲み方は想定されていない」というコメントとともに、グラスに茶色い液体が入った画像を埋め込んだツイートが拡散した。7月7日現在、表示回数が966万回以上、リツイート件数が6660件以上となっている。

返信欄ではツイートした本人が「水出しOKな商品もあります」と補足している。「コーヒーは必ず【焙煎】って過程を経るけどお茶は基本的にないのか」との声がある一方で、「デマ撒き散らすの楽しいか?」など反論するコメントもある。
検証過程
検証対象のツイートで述べられている「水出し」とは、冷水で茶葉を抽出する飲み方のことだ。日本ファクトチェックセンター(JFC)は、以下の2点について検証した。
- 紅茶は日本に輸入されるときに農薬検査はするが細菌検査はしない
- 検査をしない理由は、熱湯で淹れて飲むことが前提で、熱湯によって殺菌されるため
厚生労働省食品監視安全課輸入食品安全対策室は、海外から食品を輸入する際の検査について以下のように説明した。
「食品等を輸入する場合、日本の食品衛生法の規定に基づき、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。この届出について全国の海空港に配置された検疫所で内容を審査し、食品衛生法に定める規格や基準に適合しているかの確認をし、過去の食中毒などを考慮して必要に応じて検査を実施しています。食品衛生法に定める規格や基準等に適合しない場合、輸入はできません」
農薬検査については「茶葉の栽培課程で使用された農薬が日本の基準値を超えて残留することが想定されますので必要に応じたモニタリング検査等を実施」するという。
「細菌検査は、紅茶独自の製法等や国内外での食中毒の発生状況等を勘案の上、現時点において、病原微生物のリスクについては探知されていないことから、モニタリング検査等は実施しておりません」
つまり、紅茶輸入の際に細菌検査はしていないが、それは「熱湯で殺菌されるから」ではなく「現状ではリスクが探知されていないから」ということだ。
水出し紅茶のリスクについて、JFCは水出し紅茶葉を販売するエカテラ・ジャパンにも話を聞いた。まず、製造方法については以下のように説明する。
「水出し紅茶で使用されている茶葉は、一般的なお湯で出す茶葉と製造方法が異なることが多いと考えられます。メーカーによって様々ですが、理由は『水出しに適した製品規格にするため』で、代表的な例として微生物規格が挙げられます」
「喫食の際、加熱工程があるかどうかで微生物規格の設定方法は変わります。その観点では、紅茶は熱湯を注いで飲用される食品であるため、その喫食方法も加味した微生物規格を各社が設定していると考えられます。また現在は法律上、水出し用紅茶原料に対する微生物規格は明確に定義されたものが存在しないため、各社が自社基準に基づいた運用を行っています」
各社で製造方法は異なるという前提の上で、細菌のリスクとその対応について、以下のように述べた。
「微生物は食品に存在してはならないもののように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。目に見えないだけで食品や飲料に含まれるものをはじめ我々の生活空間に多く存在し、一切の微生物を喫食シーンから排除することは不可能です。一言に微生物と言っても多くの種類が存在し、いわゆる食中毒の原因となるのはこの一部に限られます。そのためメーカーは食品の特性や喫食のされ方に応じて、微生物規格(種類や上限量)を管理しています」
「水出し製品に限らず、抽出したお茶は長期保管せずに可能な限り速やかに消費する、ということが注意点です」
判定
紅茶が日本に輸入されるとき、細菌の検査はない。しかしその理由は、過去の食中毒等危害の発生状況等を考慮し、現時点で紅茶の病原微生物リスクが確認されていないからだ。そのため、不正確と判定した。
検証:鈴木刀磨
編集:古田大輔、藤森かもめ
判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。